
舟運とは、舟を使って川で物を運ぶことをいいます。
明治時代に鉄道がしかれ、列車や自動車で物を運ぶようになるまでは、舟を使い、川や海で物を運んでいました。
舟運についてもう少し詳しくみていきましょう。
関川の舟運
関川でも、舟でたくさんの物を運んでいました。
牛や馬を使って運ぶより、舟で運ぶ方が量も多く、運ぶ代金も安かったからです。
関川は、直江津で日本海へ出る大きな川です。ですから支流とよばれるたくさんの川が流れこみます。舟運では、支流が流れこむ場所を、川舟が着く終点として「津」(川湊)と名付けていました。
矢代川との合流点は、特に「老津」とよばれました。上杉時代、川舟は殿様におさめる米を中心に運ぶようになってきました。
上越市史によると、江戸時代(17世紀) 、高田の藩主が松平光長の時には、関川のそこをさらい、今町(今の直江津)から広島(もと和田村、今は新井市)田井(板倉町)までを舟の通れる区いきにしました。
舟子と舟つなぎ石
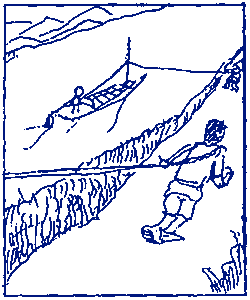 行きは、川の流れにのって、船頭さんがさおでくだります。しかし、帰りは流れにさからいます。舟はどうやってもどってきたのでしょう。
行きは、川の流れにのって、船頭さんがさおでくだります。しかし、帰りは流れにさからいます。舟はどうやってもどってきたのでしょう。
じつは、「舟子」と呼ばれる舟を引く人が、土手を歩いて綱で舟を引いて上りました。とても力のいる仕事ですね。
広島の五社神社には、「舟つなぎ石」とよばれる石があります。
この石は、もともと、関川のほとりにあり、舟運が行われていたことをしめす大切なものだったそうです。この石には穴があいていて、舟を川におくときに、舟につなをむすんで、舟が流れないようにしました。つまり、碇(いかり)の役目をしていました。
関川で使われた川舟のことは、建設省の『関川のおいたち』に書かれているように、深くしずまない仕組みで、川ヘの出入りや浅い川で物を運ぶのにつごうがよいものでした。
木島川岸から今町みなとへ
新井市史によると、「木島川岸より今町みなと(今の直江津)まで川道が3里27町(1里=4km、1町=109m なので、約15kmとなります) で、その運賃は100石(1石=150kg なので、1500kgとなります) につき、1石3升(154.5kg) で・・・」 とあります。和田のうち、関川ぞいの地域でとれた米は木島に集められ、そこから舟にのせて今町湊へ運ばれていたのだと思います。
また、新井の地域は、前年までに米を地域ごとにくら(郷倉)に入れておき、次の年の春、雪消えで水が多いときに運んでいたようですから、和田でも同じようにしていたと考えられます。
明治6年(1873)には、茶屋町に商船会社をつくり、関川と矢代川を利用して川舟で物を運ぶ仕事を始めた人がいました。
しかし、列車や自動車でものを運ぶようになってからは、舟運がどんどんへって、明治30年ごろには、関川を利用する舟は見られなくなりました。

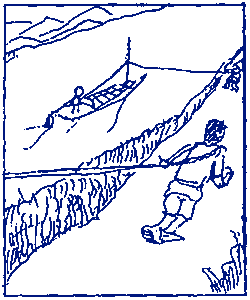 行きは、川の流れにのって、船頭さんがさおでくだります。しかし、帰りは流れにさからいます。舟はどうやってもどってきたのでしょう。
行きは、川の流れにのって、船頭さんがさおでくだります。しかし、帰りは流れにさからいます。舟はどうやってもどってきたのでしょう。